| 発信 | 発信者 | 発信内容 |
2015.03.10
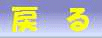 |
千葉 |
神道は宗教なのに「教」ではなく 「道」が付く
多分、全ての宗教には「教」が付いている。
ところが、神道にも「道」が付いており、「教」ではない。なぜだろう。
キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教、儒教、・・・。なるほどそうだ。
宗教には、(「教」え)である「教典」があり、開祖が居て、聖職者が「説教」をする。
その教えは厳しく、排他的でもある。時には、宗教間ばかりでなく、宗派間でも争い戦火を交える。
また、政治の道具にされるばかりか、政治を行おうとすることもある。
何故かお節介な活動が有って「布教」「宣教」「聖戦」で外部に打って出る行いをする。
一般用語で云えば「内政干渉」「侵略」だ。「解放」もある。そして、異教徒や異宗派をも殺害もする。
勿論、夫々の教徒の方々が、私達はそうではないと否定する信者も多いと承知している。
そんなあなたなら、以下の話を夫々の信者の立場でも理解して頂けると思う。
日本には神道があって、前進の古神道を併せれば、2000年超えの歴史を持つ宗教である。
仏教、道教、儒教、陰陽五行などが外来し、神仏習合の歴史を経てきたのに、現在でも神道には「教典」も「開祖」も
存在しない。従って、(「教」え)がないので「布教」もない。
とは言っても、歴代天皇から今上天皇まで毎日に仕事として「祈り」があるらしいし、私達も神社にお参りをする。
やっぱり宗教なのだ。
何を祀り、何を祈るかと言うと、八百万神の中の一神か複数神で、各人が信じる神である。
日本の神の特徴は、
・神がこの世(宇宙空間)を創造したのではなく、この世に神が生まれた。
・神はこの世の全ての物、全ての物理現象、全ての概念や思想に居る。神はそれら自体ではなく、それらに宿る。
・神は見えないが、神は神を生み、国土を生み、天皇を生み、人間を生んだ。
つまり、神道の神は未知の範囲、この世の既存を認め、変化のあるものを神の仕業と解釈した。
にも拘わらず、神が「国生み」したとは、興味深い。陸地は既存ではなかったのである。
陸地が変化すると認知していたからと思われる。
このような宗教である神道の「道」とは何を求めて祈るのか。
日本には「心技体」と言う言葉がある。職業でもスポーツでも芸術でもあらゆるものに通じて使われる。
殊更に、柔道、剣道、弓道、茶道、弓道などの「道」から派生したものと思われる。
各々の「道」では、その「道」が完全なものに成る為には、己の生き方を課題としている。他人ではないのだ。
全ての人に通じる言葉に、「道徳」という言葉もある。
これは多少社会性を伴うが、これもまた、己の生き方のことである。
従って、神道における「道」も同様であると考える。
天皇は日本国の生き方について祈り、個々の国民は己の生き方について祈ることになる。
即ち、国家が平和になり、個々が幸福になることを祈り、皆が「心技体」を目指す。
|
| 発信 | 発信者 | 発信内容 |
2015.02.26
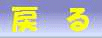 |
千葉 |
「古事記」上巻の世界感
まず、宇宙空間に最初の神 天御中主神 他二神が生まれた。(造化三神)
他の宗教の神との決定的違いは、既に宇宙空間が存在し、神が宇宙空間を造ったものではないことである。
神道における神々は唯一・絶対・最高ではなく、宇宙空間(や現代ならダークマター)の尊厳を前提にしたのである。
すなわち、イエスもアラーも他の神々も八百万の神々の内の一柱々々であり、互いに共存すると考えるのである。
一方、仏教の輪廻転生、所業無常などのように、神のような存在を否定し現世や現実を否定することはしない。
神道は、今ある現実・現状を肯定することから始まるのである。
さて、天御中主神が生まれた後、沢山の神が生まれたが、伊邪那岐、伊邪那美が生まれ、彼らが「国生み」「神生み」を
することで、更に、「古事記」の詳細な世界感が明らかになる。
「古事記」上巻の世界には、
天津神たちが住む天高原
国津神たちが住む葦原中津国
そして、死後の黄泉の国がある。
天津神は天浮橋を渡って
地上に降臨する。
伊邪那岐と伊邪那美が
地球に降り立つ足場として
淤能碁呂島(沼島)をつくり
そこで「国生み」「神生み」
を始めた。
黄泉の国で伊邪那美は
伊邪那岐を御殿から
出迎えた。伊邪那岐は約束を
破り見ることのない御殿の
中で実態を見た。
ここで「恥」「辱」の
概念が生まれた。
伊邪那岐が伊邪那美から
黄泉比良坂を下って逃れ、
坂本(上り坂の入口)を
千引岩で塞いだことから、
黄泉の国は葦原中津国より
上方にある。
伊邪那岐は禊身の最後に
天照大御神、月読命、
建速須佐之男命の三神を
生み、貴い三神と言った。
海中の海の国への道が海上に
あり、海神の宮に海神が住む。
海外の国に渡ったと記載がある。
|
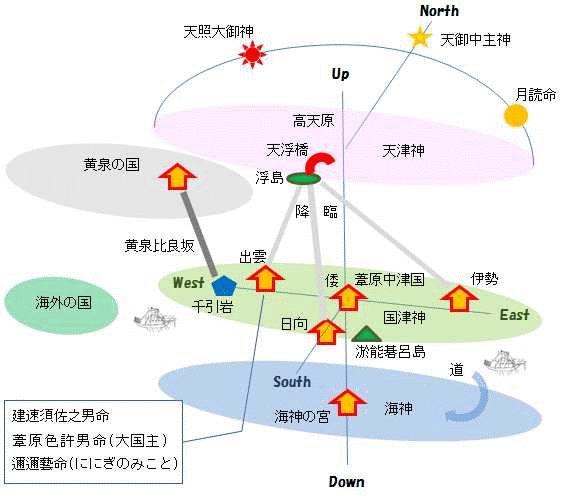 |
八百万の神々は夫々何処にでも居るのだが、上記から分かるように、天体、山や木など、物品や事象・概念など自体が神ではない。
夫々に夫々の神々が降臨しているのである。 、
|
| 発信 | 発信者 | 発信内容 |
2015.02.20
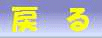 |
千葉 |
史記と歴代天皇
| 時代 | 在 位 | | 在 位 | 代数 | 追 号 | 読み | |
| 138億 | | | 138億 | 天 | Big Bang | | | |
| BC | | | | BC | 地 | | | | |
| | | | | | 開 | | 【造化三神】天御中主神 | | |
| | | | | | 闢 | | | |
| 46億BC | | | 46億BC | | 地球誕生 | 【造化三神】高皇産霊神、神産霊神 | | |
| | | 40億-38億BC | | 隕石重爆撃期 | | 46億-5.420億BC先カンブリア時代 |
| | | | 24億BC | 高 | 氷河期(1) | | 35-25億BC~シアノバクテリア |
| | | | 19億BC | | 大気組成変化 | | 27-19億BC大気:CO2→O2 |
| | | | 5.4億BC | 天 | カンブリア紀 | | 5.420億-4.883億BCカンブリア紀 |
| | | | 2.4億BC | | トリアス/ジュラ紀 | | 2.3億BC-65MBC恐竜時代 |
| | | | 1.3億BC | 原 | 白亜紀 | | |
| | | 750/460/260MBC | | 氷河期(2-4) | | |
| | | 65MBC | | 小惑星衝突 | 伊邪那岐神、伊邪那美神、淤能碁呂島 | (←沼島のこと) |
| 23MBC | | ≪大陸分離≫ | | 日本列島化 | (「国生み」「神生み」) | (←八百万の神で現代の自然生成) |
| | | | | | 国 | | | | |
| 200kBC | | | | | | | | | |
| | | | | | 生 | | | 160kBCホモ・サピエンス・イダルトゥ |
| | | | | 100kBC | | | 天照大御神、月読命、建速須佐之男命 | 100kBCホモ・サピエンス・サピエンス |
| 80kBC | 旧 | | | 80kBC | | | 倭人(自生稲、木の実の収穫と狩猟生活) | (←分子生物学で 80kBC倭人は) |
| | 石 | | | | | | | ( 支那朝鮮人とは異なる古い人種) |
| | 器 | | | | 葦 | | 伊邪那岐は淡島に幽宮(隠居) | ( 後に、大陸の人種と混雑した。) |
| | | | | | | | 大国主命 (↑淡路島の伊邪那岐神社) | |
| 17kBC | | | | 17kBC | | | (栗など豆など栽培、漁猟、家畜、土器) | 16.5kBC三内丸山遺跡に最古土器 |
| | | 新 | | | 原 | | | 大平山元Ⅰ遺跡 |
| 14kBC | 縄 | 石 | | | | | | |
| 9kBC | | 器 | | | | | (漆製品、漆塗りの弓) | (←DNA独自、漆技術大陸輸出) |
| 6kBC | | 6.3kBC | 水 | 火山爆発/寒冷化 | (縄文人南進移動、北縄文人栽培伝授) | (←東西混雑) | 7kBC 黄河文明 |
| 5kBC | | 5.5kBC | | 火山爆発/寒冷化 | (北縄文人市原から出港→ミクロネシア | →ペルーへ:5kBCの縄文土器) |
| 4kBC | | 4.5kBC | | 火山爆発/寒冷化 | (縄文人定住も:4.6kBC上中丸遺跡) | (←富士吉田市) |
| 3kBC | 文 | | 3000BC | 穂 | | (稲作の開始)() | (←) | 2kBC夏1600BC殷 |
| | | | | | | | | 1100BC~西周 |
| | | | | | | | | | 771BC~ 楚呉越 |
| 600BC | | 660BC | ~ | 585BC | | 神武元/正 . 1 | ~ | 神武76/ 3.11 | 1 | 神武 | じんむ | 神倭伊波礼琵古命 |
| | | 581BC | ~ | 549BC | | 綏靖元/ 正 . 8 | ~ | 綏靖33/ 5.10 | 2 | 綏靖 | すいぜい | 神沼河耳命 |
| | | 549BC | ~ | 511BC | | 綏靖33/ 7 . 3 | ~ | 安寧38/ 12. 6 | 3 | 安寧 | あんねい | 師木津日子玉手見命 |
| | | 510BC | ~ | 477BC | | 懿徳元/ 2 . 4 | ~ | 懿徳34/ 9. 8 | 4 | 懿徳 | いとく | |
| | 弥 | 475BC | ~ | 393BC | | 孝昭元/ 正 . 9 | ~ | 孝昭83/ 8. 5 | 5 | 孝昭 | こうしょう | |
| | | 392BC | ~ | 291BC | | 孝安元/ 正 . 27 | ~ | 孝安102/ 正. 9 | 6 | 孝安 | こうあん | 邪馬台国 |
| | | 290BC | ~ | 215BC | | 孝霊元/ 正 . 12 | ~ | 孝霊76/ 2. 8 | 7 | 孝霊 | こうれい | 登呂遺跡(静岡) |
| | | 214BC | ~ | 158BC | | 孝元元/ 正 . 14 | ~ | 孝元57/ 9. 2 | 8 | 孝元 | こうげん | 220BC秦206BC漢 |
| | | 158BC | ~ | 98BC | | 孝元57/ 11 . 12 | ~ | 開化60/ 4. 9 | 9 | 開化 | かいか | 200BC漢字伝来 |
| | 生 | 97BC | ~ | 30BC | | 崇神元/ 正 . 13 | ~ | 崇神68/ 12. 5 | 10 | 崇神 | すじん | 37BC高句麗 |
| 0 | | 29BC | ~ | 70 | | 垂仁元/ 正 . 2 | ~ | 垂仁99/ 7.14 | 11 | 垂仁 | すいにん | 57倭奴国王印 |
| | | 71 | ~ | 130 | | 景行元/ 7 . 11 | ~ | 景行60/ 11. 7 | 12 | 景行 | けいこう | 皇太子倭建命 |
| | | 131 | ~ | 190 | | 成務元/ 正 . 5 | ~ | 成務60/ 6.11 | 13 | 成務 | せいむ | |
| | | 192 | ~ | 200 | | 仲哀元/ 正 . 11 | ~ | 仲哀9/ 2. 6 | 14 | 仲哀 | ちゅうあい | 239卑弥呼(神功皇后) |
| 300 | | 270 | ~ | 310 | | 応神元/ 正 . 1 | ~ | 応神41/ 2.15 | 15 | 応神 | おうじん | 248壱与女王 |
| 300 | | 313 | ~ | 399 | | 仁徳元/ 正 . 3 | ~ | 仁徳87/ 正.16 | 16 | 仁徳 | にんとく | 391百済新羅を征服 |
| | | 400 | ~ | 405 | | 履中元/ 2 . 1 | ~ | 履中6/ 3.15 | 17 | 履中 | りちゅう | (神宮皇后) |
| | | 406 | ~ | 410 | | 反正元/ 正 . 2 | ~ | 反正5/ 正.23 | 18 | 反正 | はんぜい | |
| | 古 | 412 | ~ | 453 | | 允恭元/ 12 | ~ | 允恭42/ 正.14 | 19 | 允恭 | いんぎょう | |
| | | 453 | ~ | 456 | | 允恭42/ 12 . 14 | ~ | 安康3/ 8. 9 | 20 | 安康 | あんこう | |
| | | 456 | ~ | 479 | | 安康3/ 11 . 13 | ~ | 雄略23/ 8. 7 | 21 | 雄略 | ゆうりゃく | |
| | | 480 | ~ | 484 | | 清寧元/ 正 . 15 | ~ | 清寧5/ 正.16 | 22 | 清寧 | せいねい | |
| | | 485 | ~ | 487 | | 顕宗元/ 正 . 1 | ~ | 顕宗3/ 4.25 | 23 | 顕宗 | けんぞう | |
| | | 488 | ~ | 498 | | 仁賢元/ 正 . 5 | ~ | 仁賢11/ 8. 8 | 24 | 仁賢 | にんけん | |
| | 墳 | 498 | ~ | 506 | | 仁賢11/ 12 | ~ | 武烈8/ 12. 8 | 25 | 武烈 | ぶれつ | |
| | | 507 | ~ | 531 | | 継体元/ 2 . 4 | ~ | 継体25/ 2. 7 | 26 | 継体 | けいたい | |
| | | 531 | ~ | 535 | | 継体25/ 2 . 7 | ~ | 安閑2/ 12.17 | 27 | 安閑 | あんかん | |
| | | 535 | ~ | 539 | | 安閑2/ 12 . 17 | ~ | 宣化4/ 2.10 | 28 | 宣化 | せんか | 号名:倭国→日本国 |
| | | 539 | ~ | 571 | | 宣化4/ 12 . 5 | ~ | 欽明32/ 4.15 | 29 | 欽明 | きんめい | 五行説・仏教伝来 |
| | | 572 | ~ | 585 | | 敏達元/ 4 . 3 | ~ | 敏達14/ 8.15 | 30 | 敏達 | びだつ | |
| | | 585 | ~ | 587 | | 敏達14/ 9 . 5 | ~ | 用明2/ 4. 9 | 31 | 用明 | ようめい | |
| | 飛 | 587 | ~ | 592 | | 用明2/ 8 . 2 | ~ | 崇峻5/ 11. 3 | 32 | 崇峻 | すしゅん | 蘇我馬子 |
| | | 592 | ~ | 628 | | 崇峻5/ 12 . 8 | ~ | 推古36/ 3. 7 | 33 | 推古 | すいこ | 聖徳太子 |
| | | 629 | ~ | 641 | | 舒明元/ 正 . 4 | ~ | 舒明13/ 10. 9 | 34 | 舒明 | じょめい | 604憲法17条 |
| | | 642 | ~ | 645 | | 皇極元/ 正 . 15 | ~ | 大化元/ 6.14 | 35 | 皇極 | こうぎょく | |
| | | 645 | ~ | 654 | | 大化元/ 6 . 14 | ~ | 白雉5/ 10.10 | 36 | 孝徳 | こうとく | 中大兄皇子、鎌足 |
| | | 655 | ~ | 661 | | 斉明元/ 正 . 3 | ~ | 斉明7/ 7.24 | 37 | 斉明(皇極重祚) | さいめい | 645大化改新 |
| | | 668 | ~ | 671 | | 天智7/ 正 . 3 | ~ | 天智10/ 12. 3 | 38 | 天智 | てんじ | 670庚午年籍(戸籍) |
| | 鳥 | 671 | ~ | 672 | | 天智10/ 12 . 5 | ~ | 天武元/ 7.23 | 39 | 弘文 | こうぶん | 672壬申の乱 |
| | | 673 | ~ | 686 | | 天武2/ 2 . 27 | ~ | 朱鳥元/ 9. 9 | 40 | 天武 | てんむ | |
| | | 690 | ~ | 697 | | 持統4/ 正 . 1 | ~ | 文武元/ 8. 1 | 41 | 持統 | じとう | |
| 710 | | 697 | ~ | 707 | | 文武元/ 8 . 1 | ~ | 慶雲4/ 6.15 | 42 | 文武 | もんむ | 701大宝律令 |
| 710 | | 707 | ~ | 715 | | 慶雲4/ 7 . 17 | ~ | 霊亀元/ 9. 2 | 43 | 元明 | げんめい | 712太安万呂/古事記 |
| | | 715 | ~ | 724 | | 霊亀元/ 9 . 2 | ~ | 神亀元/ 2. 4 | 44 | 元正 | げんしょう | 720舎人親王/日本書紀 |
| | | 724 | ~ | 749 | | 神亀元/ 2 . 4 | ~ | 天平勝宝元/ 7. 2 | 45 | 聖武 | しょうむ | |
| | 奈 | 749 | ~ | 758 | | 天平勝宝元/ 7 . 2 | ~ | 天平宝字2/ 8. 1 | 46 | 孝謙 | こうけん | |
| | | 758 | ~ | 764 | | 天平宝字2/ 8 . 1 | ~ | 天平宝字8/ 10. 9 | 47 | 淳仁 | じゅんにん | 759大伴家持/万葉集 |
| | 良 | 764 | ~ | 770 | | 天平宝字8/ 10 . 9 | ~ | 宝亀元/ 8. 4 | 48 | 称徳(孝謙重祚) | しょうとく | |
| | | 770 | ~ | 781 | | 宝亀元/ 10 . 1 | ~ | 天応元/ 4. 3 | 49 | 光仁 | こうにん | |
| 794 | | 781 | ~ | 806 | | 天応元/ 4 . 3 | ~ | 大同元/ 3.17 | 50 | 桓武 | かんむ | |
| 794 | | 806 | ~ | 809 | | 大同元/ 3 . 17 | ~ | 大同4/ 4. 1 | 51 | 平城 | へいぜい | |
| | | 809 | ~ | 823 | | 大同4/ 4 . 1 | ~ | 弘仁14/ 4.16 | 52 | 嵯峨 | さが | |
| | | 823 | ~ | 833 | | 弘仁14/ 4 . 16 | ~ | 天長10/ 2.28 | 53 | 淳和 | じゅんな | |
| | | 833 | ~ | 850 | | 天長10/ 2 . 28 | ~ | 嘉祥3/ 3.21 | 54 | 仁明 | にんみょう | |
| | | 850 | ~ | 858 | | 嘉祥3/ 3 . 21 | ~ | 天安2/ 8.27 | 55 | 文徳 | もんとく | |
| | | 858 | ~ | 876 | | 天安2/ 8 . 27 | ~ | 貞観18/ 11.29 | 56 | 清和 | せいわ | |
| | | 876 | ~ | 884 | | 貞観18/ 11 . 29 | ~ | 元慶8/ 2. 4 | 57 | 陽成 | ようぜい | |
| | 平 | 884 | ~ | 887 | | 元慶8/ 2 . 4 | ~ | 仁和3/ 8.26 | 58 | 光孝 | こうこう | |
| | | 887 | ~ | 897 | | 仁和3/ 8 . 26 | ~ | 寛平9/ 7. 3 | 59 | 宇多 | うだ | |
| | | 897 | ~ | 930 | | 寛平9/ 7 . 3 | ~ | 延長8/ 9.22 | 60 | 醍醐 | だいご | |
| | | 930 | ~ | 946 | | 延長8/ 9 . 22 | ~ | 天慶9/ 4.20 | 61 | 朱雀 | すざく | |
| | | 946 | ~ | 967 | | 天慶9/ 4 . 20 | ~ | 康保4/ 5.25 | 62 | 村上 | むらかみ | |
| | 安 | 967 | ~ | 969 | | 康保4/ 5 . 25 | ~ | 安和2/ 8.13 | 63 | 冷泉 | れいぜい | |
| | | 969 | ~ | 984 | | 安和2/ 8 . 13 | ~ | 永観2/ 8.27 | 64 | 円融 | えんゆう | |
| | | 984 | ~ | 986 | | 永観2/ 8 . 27 | ~ | 寛和2/ 6.23 | 65 | 花山 | かざん | |
| | | 986 | ~ | 1011 | | 寛和2/ 6 . 23 | ~ | 寛弘8/ 6.13 | 66 | 一条 | いちじょう | |
| | | 1011 | ~ | 1016 | | 寛弘8/ 6 . 13 | ~ | 長和5/ 正.29 | 67 | 三条 | さんじょう | |
| | 時 | 1016 | ~ | 1036 | | 長和5/ 正 . 29 | ~ | 長元9/ 4.17 | 68 | 後一条 | ごいちじょう | |
| | | 1036 | ~ | 1045 | | 長元9/ 4 . 17 | ~ | 寛徳2/ 正.16 | 69 | 後朱雀 | ごすざく | |
| | | 1045 | ~ | 1068 | | 寛徳2/ 正 . 16 | ~ | 治暦4/ 4.19 | 70 | 後冷泉 | ごれいぜい | |
| | | 1068 | ~ | 1072 | | 治暦4/ 4 . 19 | ~ | 延久4/ 12. 8 | 71 | 後三条 | ごさんじょう | |
| | 代 | 1072 | ~ | 1086 | | 延久4/ 12 . 8 | ~ | 応徳3/ 11.26 | 72 | 白河 | しらかわ | |
| | | 1086 | ~ | 1107 | | 応徳3/ 11 . 26 | ~ | 嘉承2/ 7.19 | 73 | 堀河 | ほりかわ | |
| | | 1107 | ~ | 1123 | | 嘉承2/ 7 . 19 | ~ | 保安4/ 正.28 | 74 | 鳥羽 | とば | |
| | | 1123 | ~ | 1141 | | 保安4/ 正 . 28 | ~ | 永治元/ 12. 7 | 75 | 崇徳 | すとく | |
| | | 1141 | ~ | 1155 | | 永治元/ 12 . 7 | ~ | 久寿2/ 7.23 | 76 | 近衛 | このえ | |
| | | 1155 | ~ | 1158 | | 久寿2/ 7 . 24 | ~ | 保元3/ 8.11 | 77 | 後白河 | ごしらかわ | |
| | | 1158 | ~ | 1165 | | 保元3/ 8 . 11 | ~ | 永万元/ 6.25 | 78 | 二条 | にじょう | |
| | | 1165 | ~ | 1168 | | 永万元/ 6 . 25 | ~ | 仁安3/ 2.19 | 79 | 六条 | ろくじょう | |
| | | 1168 | ~ | 1180 | | 仁安3/ 2 . 19 | ~ | 治承4/ 2.21 | 80 | 高倉 | たかくら | |
| | | 1180 | ~ | 1183 | | 治承4/ 2 . 21 | ~ | 寿永2/ 8.20 | 81 | 安徳 | あんとく | |
| 1185 | | 1183 | ~ | 1198 | | 寿永2/ 8 . 20 | ~ | 建久9/ 正.11 | 82 | 後鳥羽 | ごとば | |
| | | 1198 | ~ | 1210 | | 建久9/ 正 . 11 | ~ | 承元4/ 11.25 | 83 | 土御門 | つちみかど | |
| | | 1210 | ~ | 1221 | | 承元4/ 11 . 25 | ~ | 承久3/ 4.20 | 84 | 順徳 | じゅんとく | |
| | | 1221 | ~ | 1221 | | 承久3/ 4 . 20 | ~ | 承久3/ 7. 9 | 85 | 仲恭 | ちゅうきょう | |
| | | 1221 | ~ | 1232 | | 承久3/ 7 . 9 | ~ | 貞永元/ 10. 4 | 86 | 後堀河 | ごほりかわ | |
| | 鎌 | 1232 | ~ | 1242 | | 貞永元/ 10 . 4 | ~ | 仁治3/ 正. 9 | 87 | 四条 | しじょう | |
| | | 1242 | ~ | 1246 | | 仁治3/ 正 . 20 | ~ | 寛元4/ 正.29 | 88 | 後嵯峨 | ごさが | |
| | | 1246 | ~ | 1259 | | 寛元4/ 正 . 29 | ~ | 正元元/ 11.26 | 89 | 後深草 | ごふかくさ | |
| | 倉 | 1259 | ~ | 1274 | | 正元元/ 11 . 26 | ~ | 文永11/ 正.26 | 90 | 亀山 | かめやま | |
| | | 1274 | ~ | 1287 | | 文永11/ 正 . 26 | ~ | 弘安10/ 10.21 | 91 | 後宇多 | ごうだ | |
| | | 1287 | ~ | 1298 | | 弘安10/ 10 . 21 | ~ | 永仁6/ 7.22 | 92 | 伏見 | ふしみ | |
| | 時 | 1298 | ~ | 1301 | | 永仁6/ 7 . 22 | ~ | 正安3/ 正.21 | 93 | 後伏見 | ごふしみ | |
| | | 1301 | ~ | 1308 | | 正安3/ 正 . 21 | ~ | 延慶元/ 8.25 | 94 | 後二条 | ごにじょう | |
| | | 1308 | ~ | 1318 | | 延慶元/ 8 . 26 | ~ | 文保2/ 2.26 | 95 | 花園 | はなぞの | |
| | 代 | 1318 | ~ | 1339 | | 文保2/ 2 . 26 | ~ | 延元4/ 8.15 | 96 | 後醍醐 | ごだいご | |
| | | 1339 | ~ | 1368 | | 延元4/ 8 . 15 | ~ | 正平23/ 3.11 | 97 | 後村上 | ごむらかみ | |
| | | 1368 | ~ | 1383 | | 正平23/ 3 . 11 | ~ | 弘和3/ 10.27 | 98 | 長慶 | ちょうけい | |
| | | 1383 | ~ | 1392 | | 弘和3/ 10 . 27 | ~ | 明徳3/閏10. 5 | 99 | 後亀山 | ごかめやま | |
| 1333 | | 1331 | ~ | 1333 | | 元徳3/ 9 . 20 | ~ | 正慶2/ 5.25 | 北朝1 | 光厳(北朝) | こうごん | |
| 1336 | | 1336 | ~ | 1348 | | 建武3/ 8 . 15 | ~ | 貞和4/ 10.27 | 北朝2 | 光明(北朝) | こうみょう | |
| | | 1348 | ~ | 1351 | | 貞和4/ 10 . 27 | ~ | 観応2/ 11. 7 | 北朝3 | 崇光(北朝) | すこう | |
| | | 1352 | ~ | 1371 | | 文和元/ 8 . 17 | ~ | 応安4/ 3.23 | 北朝4 | 後光厳(北朝) | ごこうごん | |
| | 室 | 1371 | ~ | 1382 | | 応安4/ 3 . 23 | ~ | 永徳2/ 4.11 | 北朝5 | 後円融(北朝) | ごえんゆう | |
| | | 1382 | ~ | 1412 | | 弘和2/ 4 . 11 | ~ | 応永19/ 8.29 | 100 | 後小松 | ごこまつ | |
| | | 1412 | ~ | 1428 | | 応永19/ 8 . 29 | ~ | 正長元/ 7.20 | 101 | 称光 | しょうこう | |
| | | 1428 | ~ | 1464 | | 正長元/ 7 . 28 | ~ | 寛正5/ 7.19 | 102 | 後花園 | ごはなぞの | |
| | 町 | 1464 | ~ | 1500 | | 寛正5/ 7 . 19 | ~ | 明応9/ 9.28 | 103 | 後土御門 | ごつちみかど | |
| | | 1500 | ~ | 1526 | | 明応9/ 10 . 25 | ~ | 大永6/ 4. 7 | 104 | 後柏原 | ごかしわばら | |
| | | 1526 | ~ | 1557 | | 大永6/ 4 . 29 | ~ | 弘治3/ 9. 5 | 105 | 後奈良 | ごなら | |
| 1573 | | 1557 | ~ | 1586 | | 弘治3/ 10 . 27 | ~ | 天正14/ 11. 7 | 106 | 正親町 | おおぎまち | |
| 1573 | | 1586 | ~ | 1611 | | 天正14/ 11 . 7 | ~ | 慶長16/ 3.27 | 107 | 後陽成 | ごようぜい | |
| 1600 | | 1611 | ~ | 1629 | | 慶長16/ 3 . 27 | ~ | 寛永6/ 11. 8 | 108 | 後水尾 | ごみずのお | |
| | | 1629 | ~ | 1643 | | 寛永6/ 11 . 8 | ~ | 寛永20/ 10. 3 | 109 | 明正 | めいしょう | |
| | | 1643 | ~ | 1654 | | 寛永20/ 10 . 3 | ~ | 承応3/ 9.20 | 110 | 後光明 | ごこうみょう | |
| | | 1654 | ~ | 1663 | | 承応3/ 11 . 28 | ~ | 寛文3/ 正.26 | 111 | 後西 | ごさい | |
| | 江 | 1663 | ~ | 1687 | | 寛文3/ 正 . 26 | ~ | 貞享4/ 3.21 | 112 | 霊元 | れいげん | |
| | | 1687 | ~ | 1709 | | 貞享4/ 3 . 21 | ~ | 宝永6/ 6.21 | 113 | 東山 | ひがしやま | |
| | | 1709 | ~ | 1735 | | 宝永6/ 6 . 21 | ~ | 享保20/ 3.21 | 114 | 中御門 | なかみかど | |
| | | 1735 | ~ | 1747 | | 享保20/ 3 . 21 | ~ | 延享4/ 5. 2 | 115 | 桜町 | さくらまち | |
| | | 1747 | ~ | 1762 | | 延享4/ 5 . 2 | ~ | 宝暦12/ 7.12 | 116 | 桃園 | ももぞの | |
| | | 1762 | ~ | 1770 | | 宝暦12/ 7 . 27 | ~ | 明和7/ 11.24 | 117 | 後桜町 | ごさくらまち | |
| | 戸 | 1770 | ~ | 1779 | | 明和7/ 11 . 24 | ~ | 安永8/ 10.29 | 118 | 後桃園 | ごももぞの | |
| | | 1779 | ~ | 1817 | | 安永8/ 11 . 25 | ~ | 文化14/ 3.22 | 119 | 光格 | こうかく | |
| | | 1817 | ~ | 1846 | | 文化14/ 3 . 22 | ~ | 弘化3/ 正.26 | 120 | 仁孝 | にんこう | |
| | | 1846 | ~ | 1866 | | 弘化3/ 2 . 13 | ~ | 慶応2/ 12.25 | 121 | 孝明 | こうめい | |
| 1912 | | 1867 | ~ | 1912 | | 慶応3/ 正 . 9 | ~ | 大正元/ 7.30 | 122 | 明治 | めいじ | |
| 1912 | 明 | 1912 | ~ | 1926 | | 大正元/ 7 . 30 | ~ | 昭和元/ 12.25 | 123 | 大正 | たいしょう | |
| 1926 | 大 | 1926 | ~ | 1989 | | 昭和元/ 12 . 25 | ~ | 昭和64/ 1. 7 | 124 | 昭和 | しょうわ | |
| 1989 | 平 | 1989 | ~ | | | 昭和64/ 1 . 7 | ~ | | 125 | 今上 | きんじょう | |
|
| 発信 | 発信者 | 発信内容 |
2015.02.18
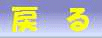 |
千葉 |
神道の祭り事と祝日
| 01/01 | 歳旦祭 | (さいたんさい) | 年始を祝う祭祀 | 元旦、初詣 |
| 01/03 | 元始祭 | (げんしさい) | 国の繁栄を願う | 初詣 |
| 01/07 | 【五節句】人日 | (じんじつ) | 七草の節句 | 七草 |
| 01/15 | 左義長 | (さぎちょう) | 炎と共に見送る | どんど焼き |
| 02/03 | 【四節分】立春の前日 | (りっしゅん) | 88夜、210日、220日の起算日 | 立春(以前は、立夏、立秋、立冬) |
| 02/11 | 紀元節(紀元祭) | (きげんせつ) | 神武天皇即位日 | 建国記念日 |
| 02/17 | 祈年祭 | (きげんさい) | 五穀豊穣などを祈る | 時期統一なく3~4月の春祭り共に |
| 03/03 | 【五節句】上巳 | (じょうし) | 健康と厄除を願う | 桃の節句、雛祭り、よもぎ |
| 03/春分 | 春季皇霊祭 | (しゅんきこうれいさい) | 天皇皇族の忌日 | 春分の日 |
| 04/29 | 旧天長節(昭和祭) | (てんちょうせつ) | 昭和天皇誕生日 | みどりの日(昭和の日) |
| 05/05 | 【五節句】端午 | (たんご) | 子供の健やかな成長を祈願 | 子供の日、菖蒲の節句、ちまき |
| 07/07 | 【五節句】七夕 | (しちせき・たなばた) | 農耕儀礼や祖霊信仰 | 七夕、素麺 |
| 08/15 | 盆 | (ぼん) | 祖先の霊を祀る | 盆 |
| 09/09 | 【五節句】重陽 | (ちょうよう) | 邪気を払い長寿を願う | 菊の節句、菊酒 |
| 09/15 | 十五夜 | (じゅうごや) | 9/13の十三夜と共に月を愛でる | 中秋の名月、観月(かんげつ) |
| 10/17 | 神嘗奉祝祭 | (かんなめほうしゅくさい) | 天照大御神にその年の新穀を奉る | 新穀を召し上がっていただく |
| 11/03 | 旧天長節(明治祭) | (てんちょうせつ) | 明治天皇誕生日 | 文化の日 |
| 11/秋分 | 秋季皇霊祭 | (しゅうきこうれいさい) | 天皇皇族の忌日 | 秋分の日 |
| 11/23 | 新嘗祭 | (にいなめさい) | 五穀豊穣の収穫感謝祭 | 勤労感謝の日 |
| 12/23 | 天長節(天長祭) | (てんちょうせつ) | 今上天皇誕生日 | 天皇誕生日 |
<参考>
国家単位でいくと、世界最古の国家
| 1位 | 日本国 | 約2675年(平成27年現在)・・・ギネス認定 |
| 2位 | デンマーク | 約1100年 |
| 3位 | 英国 | 約900年 |
*エチオピアの革命(1974年)以前は、エチオピアが1位であった。
|
| 発信 | 発信者 | 発信内容 |
2015.02.18
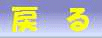 |
千葉 |
伊弉諾(いざなぎ)と伊弉冉(いざなみ)の国生み・神生み
| 淤能碁呂島 | (オノゴロ島) | 天の沼矛(あまのぬぼこ)から滴る
沼島(ぬしま):淡路島の南4.6km | |
| ┌天の御柱 | (あまのみはしら) | 柱 | |
| └八尋殿 | (やひろどの) | 柱の倶(とも)の大きな館 | |
| | | |
| 水蛭子 | (ひるこ) | はじめの求愛・恵比寿信仰 | |
| 淡島 | (あわしま) | 求愛のやり直し | |
| | | |
| 【国生み】 ・・・全十四島 |
|
| ≪大八島国≫ | | | |
| ホノサワケの島 | | | |
| 伊予の二名の島(四国) | | 伊予の国を愛比売(エ姫) | |
| └アメノオシコロワケ | | 讃岐の国を飯依比古(イヒヨリ彦) | |
| | 阿波(粟)の国を大宜都比売(オホケツ姫) | |
| | 土佐の国を建依別(タケヨリワケ) | |
| 隠岐の三子の島 | | | |
| 筑紫の島(九州) | | 筑紫の国を白日別(シラヒワケ) | |
| | 豊の国を豊日別(トヨヒワケ) | |
| | 肥の国を建日向日豊久士比泥別(タケヒムカヒトヨクジヒネワケ) | |
| | 熊曾の国を建日別(タケヒワケ) | |
| 壱岐の島 | | | |
| └天比登都柱 | (天一つ柱) | | |
| 對馬 | | | |
| └天之狭手依比売 | (アメノサデヨリ姫) | | |
| 佐渡の島 | | | |
| 大倭豊秋津島(本州) | (おおやまととよあきつしま) | | |
| └アマツミソラトヨアキツネワケ | | | |
| ≪還り時の六島≫ | | | |
| 吉備の兒島(きびのこじま) | | | |
| └建日方別(たけひかたわけ) | | | |
| 小豆島 | | | |
| └オホノデ姫 | | | |
| 大島 | | | |
| └オホタマルワケ | | | |
| 姫(女)島 | | | |
| └天一つ根 | | | |
| 知訶島(チカの島) | | | |
| └アメノオシヲ | | | |
| 両児島(両子の島) | | | |
| └アメフタヤ | | | |
| | | |
| 【神生み】 ・・・全三十五神 |
|
| ≪十神≫ | | | |
| 大事忍男神 | (おほごとおしを) | 大仕事を終えた結びを意味 | |
| 石土毘古神 | (イハツチビコ) | 家屋の材料(石、土)の神 | |
| 石巣比売神 | (イハスヒメ) | 家屋の材料(石、土)の神 | |
| 大戸日別神 | (オホトヒワケ) | 家屋の門を司る神 | |
| 天之吹男神 | (アメノフキヲ) | 屋根を葺く動作 | |
| 大屋毘古神 | (オホヤビコ) | 屋根の神 | |
| 風木津別之忍男神 | (カザモツワケノオシヲ) | 防風からの守護神 | |
| 大綿津見神 | (おおわたつみ) | 海の神 | |
| 速秋津日子比古神 | (ハヤアキツ彦神) | 水戸の神 | |
| 速秋津日子比売神 | (ハヤアキツ姫神) | 水分の神 | |
| └┴=≪八神≫ | | 海水の神、清水の神、水分の神、水汲みの神 | |
| ≪四神≫ | | | |
| 志那都比古神 | (しなつひこ) | 風の神 | |
| └速秋津日子神 | | | |
| 久久能智神 | (くくのち) | 木の神 | |
| 大山津見神 | (おほやまつみ) | 山の神 | |
| 鹿屋野比売神 | (かやのひめ) | 野の神 | |
| └ノヅチ神 | | | |
| └┴=≪八神≫ | | | |
| | | |
| 鳥之石楠船神 | (とりのいわくすぶね) | 神が乗る舟の名を司る神 | |
| └天の鳥船 | | | |
| 大宜都比売神 | (オオゲツヒメ) | 穀物の神 | |
| 火之夜芸速男神 | (ほのやぎはやを) | 火の神 | |
| ├ホノカガ彦神 | | | |
| └火神軻遇突智 | (ホノカグツチ) | | |
| | | |
| ≪伊弉冉の子 八神≫ ・・・農産の神 | (伊弉冉:大地の神、地母神) | |
| 金山毘古神 | (かなやまひこ) | 鉱山の神(吐瀉物から) | |
| └金山比売神 | (かなやまひめ) | | |
| 波邇夜須毘古神 | (はにやすひこ) | 埴土(土)の神(はにやす:屎から) | |
| 弥都波能売神 | (はにやすひめ) | 埴土(土)の神(はにやす:屎から) | |
| 彌都波能売神 | (ミツハノメ) | 水の神(尿から) | |
| 和久産巣日神 | (ワクムビ) | 穀物や養蚕を司る神(尿から) | |
| └┴=豊宇気毘売神 | (とようけびめ) | 食物・穀物を司る女神 | |
| | | |
| 【黄泉の国行き】 |
|
| 泣澤女神 | (なきさわめ) | 涙から | |
| ≪火之夜芸速男神の八神≫ | | 血から | |
| 建御雷之男神 | (たけみかずちのお) | 雷神、剣の神 | |
| ≪火之夜芸速男神の八神≫ | | 体の部位から | |
| | *伊弉諾の剣:十拳の剣(十束剣「天之尾羽張(アメノオハバリ)」) | |
| | | |
| 【身禊(みそぎ)】 |
|
| ≪脱衣の十二神≫ | | 身禊の際に脱いだ衣類から | |
| ≪身禊の十神≫ | | 身禊の際に現れた神 | |
| ≪二神≫ | | 黄泉の国で汚れた垢から | |
| ≪身禊二神≫ | | 禍を直そう為に現れた | |
| ≪水底二神≫┐ | | 底津綿津見、底筒之男 | |
| ≪海中二神≫┤ | | 中津綿津見、中筒之男 | |
| ≪水面二神≫┤ | | 表津綿津見、表筒之男 | |
| 綿津見の三神 | (わたつみ) | 安曇氏の祖先神 | |
| 筒之男の三神 | (づつのを) | 住吉神社の三座の神様 | |
| ≪貴い御子三神≫ | |
| 天照大御神 | (あまてらすおおみ) | 天(高天原)の神(左目を洗う) | |
| 月読命 | (つきよみ) | 夜の神(右目を洗う) | |
| 建速須佐之男命 | (たけはやすさのおのみこと) | 海の神→暴風の神、淡路多賀社に(鼻を洗う)、 | |
| | | |
|
| 発信 | 発信者 | 発信内容 |
2015.01.21
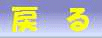 |
千葉 |
古事記による 天地開闢・高天原の神々
宇宙(138億年前)から高天原(46億年前)が出来る迄の神様
| | | | | |
| 造化三神 | 天御中主神 | (アメノミナカヌシ) | 全ての中心となる神 妙見信仰 |
| (ゾウカサンシン) | 高皇産霊神 | (タカムスビ) | 高天原の中心的な神 天孫降臨で司令塔的 |
| 神産霊神 | (カミムスビ) | 出雲の中心的な神 少彦名神は子 |
| 別天津神 | 宇摩志阿斯訶備比古遅神 | (ウマシアシカビヒコヂ) | 原始混沌の中から宇宙秩序の中心 |
| (トコアマツカミ) | 天之常立神 | (アメノトコタチ) | 宇宙より地球に至るまでを司る神 |
| 神世七代 | 国之常立神 | (クニノトコタチノ) | 国土の床(とこ、土台、大地)の出現を表す神 |
| (カミノヨナナヨ) | 豊雲野神 | (トヨクモノ) | 原野が産まれた様子の神 九州北部 |
| 宇比地邇神 | (ウヒヂニ) | 須比智邇神 | (スヒヂニ) | 泥と砂土 大地がやや形成した状態の神 |
| 角杙神 | (ツノグヒ) | 活杙神 | (イクグヒ) | 生ける万物が生まれたことを表わす神 |
| 意富斗能地神 | (オホトノジ) | 大斗乃辧神 | (オホトノベ) | 大地が完全に凝固時を神格化 男女の性器 |
| 淤母陀流神 | (オモダル) | 阿夜訶志古泥神 | (アヤカシコネ) | 大地の表面が完成、成立を表す神 愛の告白 |
| 伊邪那岐神 | (イザンギ) | 伊邪那美神 | (イザナミ) | 最初の夫婦神 人類の起源神 |
| 138億BC |
46億BC |
|
|
|
660BC |
|
0 |
2015 |
| 天地開闢 |
高天原 |
葦原水穂國(大国主) |
(1)神武天皇~(125)今上天皇 |
|
| BigBang |
Earth |
|
旧石器 |
縄文 |
弥生 |
古墳/飛鳥~平成 |
|
|
| 発信 | 発信者 | 発信内容 |
2015.01.14
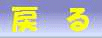 |
千葉 |
神秘の国に神秘の神道ありき
欧米人に神秘の国と呼ばれる日本、
経験のない異質な日本の人生観や美観に触れて、神秘に思うのだろう。
同じ極東の中国人や支那人、朝鮮人の方が欧米人には遥かに理解し易く、御し易いようだ。
最も、同じ極東の中国人や支那人、朝鮮人ですら、日本の心を理解し得ないようである。
日本には、「古事記」の時代以前から八百万の神が居て、神が近い存在にある。
日本では、良い者も悪い者も異質な者も亡くなると神になることが出来る。 そこでの祈りには、過去も未来もない、現世を祈る。
一方、自然のささやき、虫の音、葉や花の散るさまにも心を打たれる感受性もある。また、非対称や不規則に対する美観も存在する。
わび、さび と云う無いことへの美観もある。それらを短い歌で表現する。
大和言葉(国語)は他国の言語を吸収し進化して、他の言語に無い世界を表現し、あらゆる全てを表現できる言語に成長たので、
日本語を正確に他の言語に翻訳することが難しくなった。
愈々欧米人には理解することは難しいであろう。
その証に、戦後に「天皇の人間宣言」を強いられた。 しかし、それでも天皇も神になれる。 欧米人の誤解に基づく出来事だ。
そこには根底に、日本独自の神道がある。
では、神道、仏教、キリスト教、イスラム教を比較してそれらの違いから理解してみたい。
|
神 道 | 仏 教 | キリスト教 | イスラム教 |
| 開祖 |
(無) | 釈迦(仏陀) | イエス | ムハンマド |
| 崇拝対象 |
八百万の神 | 釈迦、観音など(偶像) | イエス(偶像) | アッラーフ(唯一最高位神) |
| 教典 |
(無) | 経典 | 聖書 | コーラン |
| 聖職者 |
神主、巫女 | 僧 | 神父 | ウラマー |
| 聖職者の仕事 |
歳事、社務、祈祷など | 経を唱え | 聖書を読み解く | 宗教教育の先生 |
|
- | 説教 | 説教 | 説教 |
| 説教内容 |
- | 諸行無常、煩悩、解脱 | 神は絶対的存在 | 神は絶対的存在 |
| 祈りの背景 |
現世の幸福 | 善行で死後の安楽に | 皆罪人、死後の神が救う | 皆罪人、死後の神が救う |
|
| | 神が絶対 | 神以外には平伏し禁止 |
| 祈りの内容 |
自然・道具へ感謝、畏敬 | 仏の力で厄除・除難を | 神への賛美、感謝、嘆願、 | 絶対的アッラーフへの |
|
招福祈願、厄除祈念 | 僧侶が加持 | 執成し、静聴、悔改 | 賛美、感謝、嘆願、 |
|
神々と人の交流 | 願掛け | 決意表明、懺悔、告白 | 執成し、静聴、悔改 |
| 信者の死後 |
御霊は家の守護神に | 故人は極楽浄土に | 魂は神の御元に | 魂は神の御元に |
| 宗教施設 |
神社 | 寺 | 教会 | モスク |
| 施設の役割 |
祈る場 | 鎮魂の場 | 懺悔、説教の場 | 祈る場 |
|
- | 悟りを目指す人が暮らす | 教育の場 | - |
| 信者の作法 |
二拝二拍手一拝 | 合掌 | 合掌 | シャハーダ(信仰告白) |
|
| | | サラー(日5回の拝礼) |
|
| | | ラマダーン(断食) |
|
| | | ハッジ(巡礼) |
| | | | ザカート(喜捨:施し)の5行 |
| 布教活動 |
(無:自発的) | 法師が布教 | 宣教師が布教 | ウラマーが教育 |
|
| | | 聖戦でも布教 |
| 宗派 |
(無) | 小乗、大乗、 | カソリック | シーア派 |
|
| 禅 | プロテスタント | スンニー派 |
|
| ・・・ | ギリシャ正教 | ・・・ |
| 宗教宗派対立 |
(無) | 温厚 | 対立 | 対立 |
神道って、現状を肯定し、全てを許容して現世の幸福を祈る。 唯一絶対が無く強要もせず、最も平和的宗教だね。
一方、教典も無く、説教もなく、信者を縛らないから理解し難いんだね。
現世は神頼み、死後は仏頼みの日本人のご都合主義も面白い。
|